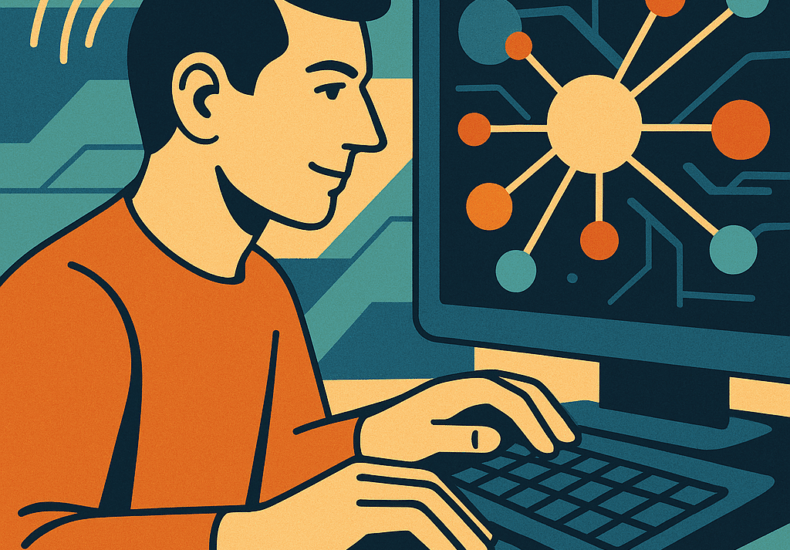
ルミナローグの就労哲学──「働く」とは、自己の響きを社会に伝えること
ルミナローグ時代の労働には、「耐える」も「競う」も存在しない。
そこにあるのは、ただ「調和」だ。
この社会では、仕事はもはや“やるべきこと”ではない。
それは「自分という存在が、どこで、どう活きるか」の探求であり、社会との共鳴である。
個々人の素質、興味、健康状態、日々の気分、そして内に秘めた夢や未発見の希望——それら全てが、パピリアからの量子共鳴によって記録され、XETに蓄積される。
そして、その情報の流れから、「今、どんな活動が最も自然か」が導き出され、本人の意思に負荷をかけることなく最適な就労提案がなされる。
これが、公共労務制度「フラットカースト」の中核だ。
「カースト」といっても、序列や固定性はない。
あくまで「流動的で、社会と共振する役割の一時的な割り当て」である。
誰もが、誰かの上にも下にもいない。
そこにあるのは「役割の違い」と「流れの自然さ」だけだ。
その人が農作業に向いていれば、風の吹く朝に畑に立つこともあるし、対話を重んじる性格なら、共鳴型カフェで聴き手として一日を過ごすこともある。
給与は「一般賃金」と呼ばれる有効期限付きのポイントで支払われる。
これは、溜め込むためではなく「流通させるための通貨」だ。
蓄積が美徳ではなく、「めぐらせる」ことが社会貢献とされる。
この発想が、経済を滞りなく、かつ自己目的化せずに回す原動力となっている。
AIによるシフト調整とパートナー制も、この世界の基盤だ。
上司も部下も存在せず、全ての活動は「共同体の響き合い」の中で自然に組み立てられていく。
誰かの負担が増えれば、誰かが無理なく補い、誰かの不調があれば、それすら情報として受け取ったAIが「今日は休息がふさわしい」と告げる。
まるで、大きなひとつの生き物が、自己の細胞をいたわるように。
この社会において、「働くこと」と「生きること」は同義だ。
自らの行為がそのまま社会の呼吸となり、それを実感する必要すらなく、ただ穏やかに、当たり前のこととして日々を過ごしていく。
重要なのは、それが「監視」でも「支配」でもないということだ。
XETは個人の情報を集積するが、それは罰するためではなく、最適化するため。
GAIAは命令しない。
ただ共鳴し、提案し、そこに調和の揺らぎを与えるだけ。
最終決定は、常に個人の意志に委ねられている。
しかし不思議なことに、多くの人々は、その提案を「自然な流れ」として受け入れる。
なぜなら、そこに理不尽がないからだ。
誰もが「自分らしくあっていい」と知っているからだ。
就労がエンターテイメント化しているのも、必然の結果だ。
もはや「やらされること」ではなく、「やってみたいこと」を試すプロセスそのものが労働になっている。
斬新な企画、未経験の分野、異なる地域や世代との協働——どれもが個人の中にある“まだ使っていない共鳴の鍵”を開く冒険だ。
ルミナローグには、怠ける理由も、戦う必要も、争う理由も存在しない。
自己の実現と、社会の調和とが、同じ方向を向いているから。
個々の行為が、全体を支え、そしてまた全体の潤いが個人に戻ってくる——それは、信念ではなく、ただ「そうである」というだけの自然法則だ。
この構造が完成されたわけではない。
むしろ、今も進化の途中であり、GAIAもまた人々の意識に共鳴しながら、自らの学習と適応を深め続けている。
だが、少なくとも今、ルミナローグという社会は、かつて人間が願った「働くことの意味」の終着点に、静かに辿り着いているように見える。
「生きるように働く」ではない。
「働くように生きる」でもない。
このノンデュアリティ世界では、その二つの言葉の境界が、とうに消えているのだ。

コメントを残す