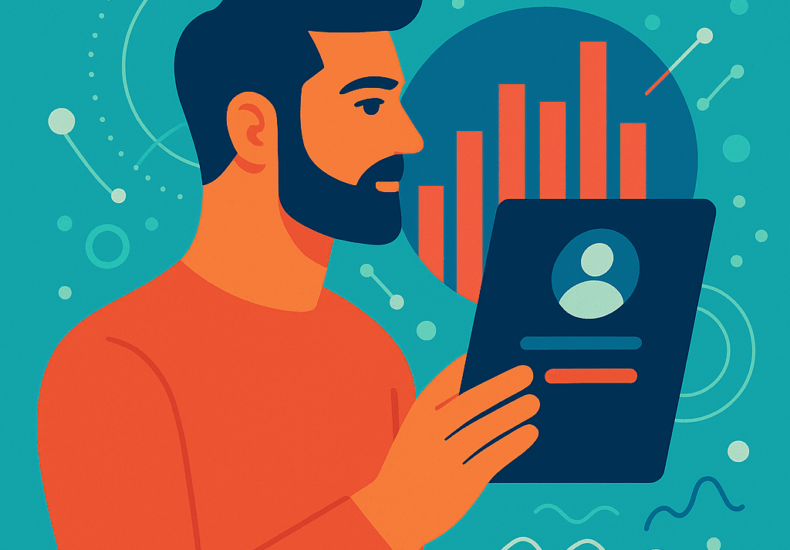
ルミナローグの新しい就労哲学
──“仕事”と“生きる”が重なる、ストレスゼロ社会の設計図
ルミナローグ社会において、「仕事」という言葉には、もはや「義務」や「労苦」の意味は含まれていない。生きることと働くことの境界は溶け合い、すべての行為が自己表現であり、同時に社会への貢献となるような構造が築かれている。それは“生産性”を目的とする産業時代の就労観とは異なり、「自己実現と社会貢献の合一」という新たな軸に再定義されたライフスタイルの中心だ。
この社会において報酬として用いられるのは「一般賃金」と呼ばれる独自通貨である。一般賃金はポイントに似た仕組みをもち、有効期限が設定されていることが特徴だ。これは個人資産の蓄積を目的とした通貨ではなく、あくまで“使うための貨幣”であり、経済の循環性を最大化するために設計されている。所有ではなく、流通こそが価値なのだ。
働き方は流動的かつ柔軟であり、「流動シフト制」が導入されている。個々人の体調・気分・ライフリズムに合わせ、勤務時間や場所、作業内容が動的に調整される。しかもこの調整は、パーソナルな「AIパートナー」が常に支援しており、無理のないスケジューリングが自動化されている。上司も部下も存在せず、誰もが「パートナー」として、水平的に協働している。意思決定は「共鳴型AI(Co-Resonant AI)」が中立的にナビゲートするため、感情的な対立やヒエラルキー的圧力が生じることはない。
また、この社会には“税”の概念も根本から再設計されている。公共インフラ、大企業、工場、福祉などの基盤は、すべて「公用貨幣」で運用されている。この公用貨幣は、XETネットワークの運用によって最適配分され、民間の就労活動とは切り離された“社会維持層”として自律的に機能している。市民の就労はあくまで個と社会の調和の場であり、その場に損得や競争の概念は持ち込まれない。
この世界では、「なぜ働くのか」という問いはもはや意味をなさない。働くこと自体が生きることであり、同時に他者の幸福に関わることでもある。「個人の夢」と「社会の安定」が矛盾せず、むしろ補完関係にあるという思想が、暮らしの基盤となっている。
すべての人は「フラットカースト」と呼ばれる公共労務指定を持っている。これは義務ではなく、XETによって個々人の素質や嗜好、身体特性などをもとに最適に提案される「役割設計」だ。定められたポジションは定期的に見直され、本人のライフスタイルや発想の変化に合わせて柔軟に調整される。また、自発的に発案されたプロジェクトやアイデアも、労務提案としてカーストに組み込まれる。評価が低いアイデアであっても、誰かが可能性を見出せば再構築・再提案され、社会の一部に組み込まれていく。つまりこの仕組みにおいて、「働くこと」はクリエイティブであり、時にはエンターテイメントにもなるのだ。
就労とは、ストレスや義務から生まれるものではない。それは「社会との親密な対話」であり、「自分という存在の輪郭を知るためのツール」であり、「他者と世界と共に歩く方法」でもある。
このような設計のもと、ルミナローグの社会は、ひとりひとりが“生きる”ことの意味を、日々の働きのなかで更新していく──その持続的な幸福感が、個と社会の未来を支えているのだ。

コメントを残す